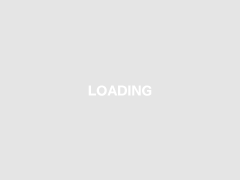イベント
ゲームAIの先端に立つ2人が現状と課題について語る。トークセッション「ゲームAI開発の舞台裏〜AIはゲームをどう変えた?これからどう変えていく?」をレポート
このイベントでは,書籍「ゲーム情報学概論」「ゲームAI技術入門」といったゲームAIの研究で知られるスクウェア・エニックス リードAIリサーチャーで日本デジタルゲーム学会理事の三宅陽一郎氏と,モリカトロン代表取締役であり,「がんばれ森川君2号」「くまうた」といったゲームとAIを組み合わせた作品を手がけた森川幸人氏がゲームとAIについて語った。
 |
課題は,AIとゲーム開発をつなげるパイプを作ること。そのために2つの分野に精通した人材の重要性が増す
モリカトロンは,娯楽にAIを活用する「エンタメAI」の研究を進める会社だ。同社はエンターテインメントとAIの可能性を探るクリエイター&エンジニア向けコミュニティとして「モリカトロンAIコネクト」を立ち上げており,「AIに興味のある人がつながれるようなイベント」(森川氏)として今回の催しが行われた。
 |
 |
今回のセッションで語られたのは,ゲーム開発とAIがパイプラインで組み合わされたことによる「機械学習元年」の到来,そしてゲームデザインとAIの双方に知見を持つ横断的な才能の必要性だ。
AIがゲーム開発の現場で活用されるようになってしばらく経つが,三宅氏は機械学習元年がやってきたと語る。
Ubisoftの「スター・ウォーズ 無法者たち」では,AIとゲームエンジンがパイプラインで組み合わされ,AIによって乗り物が安定走行できるよう機械学習が活用されたという。三宅氏はAIとゲームエンジンの融合を予想はしていたものの,「まさに今年,そのタイミングが来た」と語っていた。
機械学習自体はこれまでも開発に使われているが,「AIとゲームエンジンがパイプラインで組み合わされている」ことが大切である。今後こうした環境が整備されていくと,開発のさまざまなシーンでAIが汎用的に使えるようになっていくだろうと三宅氏は予想していた。
 |
一方日本の開発現場では,AIの導入が難しい部分があると森川氏は指摘する。開発の初期段階ではAIチームが招聘され,その可能性の大きさが歓迎されるものの,実際に作業が進むと「AIは自由過ぎてコントロールできない」と利用が控えめになっていく傾向があるそう。
これについては,海外との開発風土の違いも指摘された。海外では「新しい技術は必ずゲームを良くするはずだ」という技術主導で開発が進むため,AIの導入も積極的に行われる。しかし,日本の開発は,ゲームデザイン主導で開発が進むため,海外ほどにはAIを利用しようとしないのだ。
しかし,三宅氏は「ほとんどの優れたゲームデザインは日本から考案されているので,AIを生かした新しいゲームデザインを創出するのではないか」とも考えているそうだ。
開発者は職人的であり,それゆえにすべてのコントロールを自分が握りたがるため,ブラックボックスであるAIとは相性が良くない。
また,生成物のクオリティに関する問題もある。質の低いものが出てきてもプロンプトを工夫することで向上は図れるものの,それにも限界はある。「AIが60〜80点のものを出していても,ゲーム業界では99点のクオリティで争っている」(三宅氏)ため,そのまま使うには難しいわけだ。
そして,何かがあったら誰が責任を取るのかという問題もあり,大手メーカーほどフットワークは重くなる傾向にある。事実,大規模言語モデルがネット接続を通して学習すると,ファンタジー世界のゲームなのにコンビニの話を始めたり,スラングや差別用語を出力したりするといった課題も残っている。三宅氏は「ゲーム産業全般において,長期的には間違いなくゲームを革命する技術だが,現状はどうするかに苦労しているのが,業界全体の状況だ」と認識しているという。
 |
逆にインディースタジオにおいてAIは強力なツールとなり得る。大手メーカーが大規模開発でAIに1人分の仕事をやらせてもコストカット効果は微々たるものだが,インディースタジオでは,そもそもの人数が少ないため,その恩恵は大きい。
前述したクオリティの問題も,インディーであれば99点を出す必要もない。「質はともかく,AAAタイトルと同じくらいの量を生成できるようにはなっているため,今後は人数=ボリュームの方程式が崩れていく」と三宅氏は予想する。
大手メーカーで人間が作ったボリューム感と,生成AIを取り入れたインディーのボリューム感,ユーザーがどちらを選ぶかという局面になっていくという。
インディースタジオがAIを扱う場合,前述したUbisoftほど環境が整備されているわけではない……という問題は残るものの,これも時間が解決するだろうと三宅氏は予想する。
かつての3DCGツールにも同様の扱いづらさはあったものの,パイプラインが整備されることで一気に一般化が進んでいる。AIにも同じことが起こるだろうというわけだ。
このように現時点で開発現場におけるAI利用はまだ進んでおらず,その理由として三宅氏はUIの未整備を挙げる。
生成AIを使うにあたり,プロンプトを工夫することで望む出力を得るテクニックやPrompt Magicというツールも存在するものの,汎用的なものではない。
三宅氏は「ゲームデザインは繊細なものなので,ゲームとAIをダイレクトにつなごうと,ゲームデザインが崩壊する」と語る。AIがもっと活用されるには,AIのコードをある程度書けるうえで,ゲームデザインとAIを橋渡しできる人物,つまり森川氏のような人がもっと必要であるという。
森川氏のモリカトロンもこうした人材「AIプランナー」を求めているものの,設立8年で一人しか応募がなかったそうだから,いかに貴重であるかが分かるだろう。
 |
そして「AIはゲームをどう変えたか」というテーマについて,三宅氏は「AI(ディープラーニング)はまだゲームを変えてはいない」,森川氏は「変えたという実感はないが,ようやく話を聞いてくれる状態にはなった」と考えているそうだ。
現状はAIでなくてもやれる部分をAIに置き換えているに過ぎないが,今後はゲームデザインのコアに機械学習が取り入れられることで,過去の作品を超えるようなゲームデザインが生まれると予想していた。
新たなゲームデザインの誕生については,小規模開発や学生からの斬新なアイデアに期待を寄せていることも語られた。
実際に,2023年のイギリスのケンブリッジで開かれたゲームAI国際サマースクールのゲームジャムでは,大規模言語モデルを用い「モンスターと戦う前にプレイヤーが言葉で説得し,テンションが下がり切ったところを一撃で仕留める」というゲームが作られたという。
確かに,大手メーカーが商品としてゲームを作るうえではなかなか出てこないアイデアだろう。
三宅氏は「AIを導入するにしても,いきなり現場で使えるようになるものではない。100個アイデアを考える中から1つをピックアップし,これをテストしていくといった取り組みが必要で,いきなり大上段に構えないほうがいい」と語る。
そして森川氏は「人間の仕事をAIにやらせるのではなく,遊びの拡張に使われていくと面白いものができるのではないのか」と期待を寄せる。
ちなみに森川氏は「最近はゲームデザインを考えるとき,なるべく生成AIを使わないようにしている」という。
エンタメAIを研究する氏の行動としては意外な印象があるが,これについては「生成AIの限界=ゲームデザインの限界になるのは危険である」と感じているからだそう。「AIを使うことでかえってアイデアが限定されているのではないか」という懸念があるようだ。
ここからは筆者の所感だが,こうした危険性は机上の空論ではないと思える。各種のツールが世に出た際は,一般化が進んでいないこともあり,どうしてもそのツールに特化した職人的かつ属人的な仕事になってしまう。
特定ツールを使いこなすテクニックだけを磨いてしまい,主流が別のツールに移ったときはさまざまな意味で大慌てすることになる光景がしばしばみられる。つまりツールを使うはずがツールに使われていたわけだ。
これを防ぐには,森川氏と三宅氏が語る「AIとゲーム開発の両方に知見を持つ人物が両者の橋渡しをした」うえで,利用者側にもAIに使われるのではなく使うという意識が必要であると感じられた。
 |
 |
世間ではAIの可能性がピックアップされる一方で,ゲーム開発ではさまざまな課題が残ること,これを解決できるのは,AIとゲーム開発に知見を持つ人間であり,両者を熟知しているからこそパイプ役になれる……というのが本講演の主旨だ。
3DCGで同様の問題があった際に,3Dモデルを作っていた人がプログラミングを覚えて「テクニカルアーティスト」というパイプ役になったように,アート畑の人が技術を学ぶことでこれらの問題が解決される可能性があるのではないかと三宅氏は語っていた。こうした人材を育成する体制の整備に期待したいところだ。
「日本デジタルゲーム学会」公式サイト
「モリカトロン」公式サイト
- この記事のURL: