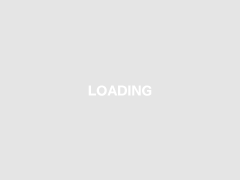イベント
[CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート
![画像集 No.001のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/001.jpg) |
日本と欧米では好まれるゲームにそれだけ違いがあるわけだが,現在開催中のCEDEC 2016で,「欧米で日本のゲームを成功させる方法 How to make Japanese games work in the West」という興味深いセッションが開催された。本稿でその模様をレポートしよう。
講演者のTeut Weidemann(テュート・ワイデマン)氏は,1980年代からゲーム業界に携わり,100を超えるタイトルを主流のプラットフォームに送り出してきた人物で,現在はオンラインゲームおよびFree-to-Playタイプのゲームのコンサルタントを生業としている。
ワイデマン氏が最初に取り上げたテーマは,「グラフィックススタイル」および「世界観の設定」だ。
日本のゲームのグラフィックススタイルはマンガやアニメに近く,たとえば顔は記号的に表現され,現実にはいない不思議な生物がマスコットとして登場することも多い。そして日本のゲームでは,「ファイナルファンタジー」シリーズに代表されるように,ファンタジーとSFの融合が普通に行われている。
しかしこれらの要素は,いずれも欧米では一部の層にしか受け入れられていないそうだ。
![画像集 No.002のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/002.jpg) |
とくにファンタジーに関しては,1964年の「指輪物語」以来,アメリカではシリアスなものと捉えられており,現在は文学の中でも2番めに大きいジャンルとなっているとのこと。そのため多くのアメリカ人は,ファンタジーをコミカルに描くことを好まないという。
また欧米のゲーマー,もしくはファンタジー愛好家の平均年齢は35歳前後である。彼らはアニメ調で描かれたファンタジーを子ども向けと判断し,見向きもしない可能性が高い。ちなみにワイデマン氏が欧米で受け入れられる正統派ファンタジーの例として挙げたのは,TVドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」である。
![画像集 No.003のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/003.jpg) |
以上の理由から,日本のゲームが欧米で成功するためには,グラフィックススタイルをもっと大人向けのシリアスなものにする必要があるとワイデマン氏は語った。
ただし欧米でも,24歳未満の若い層の中にはアニメ調グラフィックスやJRPGに抵抗のない人達が増加傾向にあるため,今後5年10年と時間が経過すれば,状況が変わるかもしれないという。
次のテーマは「ゲーマーズエデュケーション」で,ここではゲームが辿った歴史と,それがもたらしたゲームやゲーマーへの影響が語られた。
ワイデマン氏は,日本と欧米のゲームプラットフォームの推移を比較して,欧米では早くからPCゲームが普及し,2000年代にはPCオンラインゲームが台頭したのに対し,日本ではその過程がなかったと指摘。代わりに2000年代の日本におけるi-modeの登場が,その後の日本と欧米におけるモバイルゲーム普及度の違いに大きな影響を与えたとした。
![画像集 No.004のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/004.jpg) |
![画像集 No.005のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/005.jpg) |
そのもっとも顕著な部分が,ユーザーインタフェースである。i-mode向けのゲームはフィーチャーフォンの形に合わせた縦長の画面でプレイするものがほとんどだったが,ワイデマン氏は,その流れで今なお日本のスマートフォンゲームは端末を縦持ちしてプレイするものが多いのではないかとの持論を披露し,この点をもっと研究すべきであるとした。
![画像集 No.006のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/006.jpg) |
またPCに紐付かないオンラインプラットフォームとしてi-modeが普及してしまったことも,日本のゲームが独特の進化を遂げてしまった理由として挙げられた。たとえば韓国や中国では,ゲーム文化が2000年代のPCオンラインゲームの台頭以降に根付いたこともあって,プレイヤー同士が競い合うPvPコンテンツが好まれているが,日本ではそうでもない。
しかし実のところ,アメリカでもオンラインゲームのPvPコンテンツを好むのは13歳から25歳のコアゲーマーが中心とのこと。26歳以上のゲーマーになると,あまりゲームのプレイ時間が取れないことを理由に,PvEのほうを好むようになるという。結果として欧米では,ゲーマー全体の60%以上がPvPよりPvEを好むと答えたそうだ。
3つめのテーマは,「ゲームメカニクス」だ。欧米のゲーマーの多くは,ゲームの中で自分以外の“誰か”になり,ほかのプレイヤーとソーシャルな関係を結ぶことを望んでいる。そのため欧米のゲームでは,プレイヤーの「アバター」が重視されるのだが,「パズル&ドラゴンズ」(iOS / Android)のような日本のゲームは,プレイヤーネームこそあるが,誰かになるわけではない。
![画像集 No.007のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/007.jpg) |
また,欧米のゲーマーが平均35歳前後であること,そして60%以上がPvEを好むことは前述したとおりだが,さらにいうと,オンラインゲームであっても1人か少数の知人と一緒にプレイする機会が多いという。
加えてPvEを好むゲーマーの多くは,自分のプレイ環境にPvPが入り込むことを嫌う。そのため「World of Warcraft」などでは,PvPを専用フィールドで行うようになっている。さらに対戦ゲームとして人気のある「League of Legends」でも,プレイされるセッションの60%は対人戦でなく,AI対戦というデータがあるとのこと。
![画像集 No.008のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/008.jpg) |
これらをまとめてワイデマン氏は,欧米で成功するゲームメカニクスのポイントとして,「プレイヤーがほかの誰かになれるようにする」「十分な量のPvEを用意する」「PvPはPvEから隔離する」「最低2人の協力プレイを入れる」「欧米ゲームのユーザーインタフェースを研究する」という5つを挙げた。
また,こうしたゲームメカニクスを採用している欧米のゲームは,日本人からするとしっくりこないかもしれないが,なぜそうなっているのかぜひ分析してほしいとも語っていた。
4つめのテーマは「マネタイゼーション」。アジアにおいてはFree-to-Playのアイテム販売が主流だが,これは欧米だと「Pay-to-Win」と呼ばれてフェアでないと見なされる。また日本でポピュラーなガチャも,欧米ではうまくいかないケースが多いのだが,これは他人が運良くレアアイテムを獲得すると妬んでしまうという欧米人の心理によるものとのこと。
それでは欧米ではどうやってFree-to-Playのゲームを展開するのか。答えはシンプルで,ゲーム内でユーザーが時間を掛ければ,もしくはプレイの腕前が良ければ販売されているアイテムと同じものを獲得できるようにすればいいのである。このように,欧米でゲームをマネタイズするためには,ユーザーにいかにフェアであるかを感じさせる必要があるとワイデマン氏はまとめた。
![画像集 No.009のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/009.jpg) |
以上のポイントを踏まえ,ワイデマン氏は最後に,日本でヒットしたタイトルの代表的な存在である「パズル&ドラゴンズ」を欧米で成功させるための改善点リストを披露した。
・プレイヤーキャラクターを用意し,モンスター達のリーダーに据える
・冒険できるフィールドを用意する
・プレイのモチベーションを持続させるストーリーを用意する
・プレイのキーとなるモンスターは,ゲームプレイを通じて獲得できるようにする
・マネタイゼーションはフェアだと感じられる内容にする(レアアイテムの入手方法として,お金,腕前,時間のいずれかを選べるようにする)
ワイデマン氏は「このリストを一言で表現すると,『ポケットモンスター』のようなゲームにすればいいということになります」とまとめた。
そして,今回の話をヒントに欧米のゲームを研究したり,過去に欧米で生まれた大きなヒットを分析したりすると,欧米で成功するゲーム展開の糸口が見つかるのできるのではないかとして,セッションを締めくくった。
![画像集 No.010のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/010.jpg) |
CEDEC 2016関連記事一覧
- この記事のURL:







![[CEDEC 2016]パズドラをポケモンのようにすれば欧米でヒットする? 欧米で日本のゲームを成功させる方法が語られたセッションをレポート](/games/999/G999905/20160825100/TN/011.jpg)