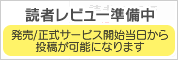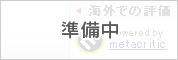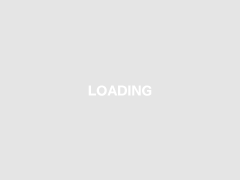プレイレポート
「ELDEN RING NIGHTREIGN」を4時間遊んで,分かったこと。約40分にRPGの“成長と達成”を詰め込んだ新世界をチェック
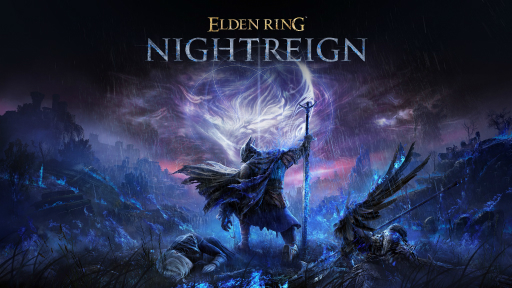 |
The Game Awards 2024で突如として公開された本作の映像は,多くのファンを驚かせた。ELDEN RINGの名を冠する作品でありながら,「DARK SOULS」のボスらしき者の姿が見え,しかもジャンルは協力型サバイバルアクションというのだから無理はない。
直後に公開された公式サイトに掲載された情報を漁り,結果として頭に浮かぶ“?”の数を増やした人も多いことだろう。
今回の先行プレイではたっぷり4時間も遊ぶことができたので,気になる要素を可能な限り調べてきた。2月14日から17日にかけて実施されるネットワークテストの参加者は,ぜひ参考にしてほしい。
なお,登場する敵などのネタバレに踏み込まないよう,本稿はシステム面の紹介に特化している。プレイフィールは最後にまとめているので,情報の内容に合わせて読み進めよう。また,試遊はPS5版を使用しているため,ボタンの表記はそちらに準拠している。
「ELDEN RING NIGHTREIGN」公式サイト
まずは,多くの人が気になっているであろう「どんなゲームなのか」「ELDEN RINGと何が違うのか」「細かな仕様はどうなっているのか」という部分を順番にまとめていこう。
NIGHTREIGNは何をするゲームなのか
端的にいうなら,本作は“仲間と協力してボスの討伐を目指すアクションゲーム”だ。プレイヤーは挑戦する「夜の王」(ボス)を選択し,オンラインで一緒に戦うメンバー(自分含めて最大3人)を集めて戦いに赴くことになる。ハンティングアクションゲームにおける討伐ミッション受注の流れを想像してもらえればイメージできるだろうか。
ただ,キャラクターのレベルは必ず1からスタートし,初期装備も固定だ。討伐対象と出撃チームが決まったら,全員が広大なフィールドに放り出されるので,そこで強力な装備品を収集しつつ,ボス討伐に向けたレベル上げをしなければならない。
 |
フィールドを探索できる時間には制限があり,一定時間が経過すると外周からダメージゾーンが迫ってくる。活動可能な範囲は最終的に小さな円形へと収束し,そこでは中ボスとの戦闘が繰り広げられる。
中ボスを撃破するとダメージゾーンが晴れ,改めて探索を行えるようになる。そのまま同じ流れを繰り返し,もう一度出現する中ボスに勝利すれば,目標となる「夜の王」(開始時に選択したボス)への挑戦権が得られる。それに打ち勝てば,晴れて討伐達成だ。
 |
まとめると,以下のような流れになる。バトルロイヤル系ゲームを全プレイヤーで協力しながら進め,ダメージゾーンが狭まった最後のエリアでPvEをする……とイメージすると分かりやすいかもしれない。なお,本作にボイスチャット機能は実装されていなかった。
| 討伐対象選択 | 1:「夜の王」の中から攻略対象を選択 2:オンラインで仲間を募る ・合言葉による絞り込み可 3:8人の「夜渡り」から使用キャラクターを選択 ・仲間の選択を確認したうえで変更可 4:フィールドに向けて出撃 ・1人での出撃も可 |
| ↓ | |
| フィールド探索 (1回目) |
1:レベル1かつ初期装備状態で開始 ・開始位置はランダム ・飛行状態で開始。着地位置は調整可 2:探索して敵を撃破し,経験値や装備を確保 ・フィールドの形状,敵やアイテム配置はランダム 3:一定時間経過で外周にダメージゾーンが出現 ・ダメージゾーンに触れると継続ダメージ 4:ダメージゾーンが時間経過で拡大 ・最終的に活動可能範囲が小さな円形に収束 |
| ↓ | |
| 中ボス討伐 (1回目) |
1:ダメージゾーン最大時に中ボス出現 ・出現する中ボスの種類はランダム 2:撃破時に報酬を得る ・報酬は選択式で,仲間全員が得られる 3:ダメージゾーンが晴れる |
| ↓ | |
| フィールド探索 (2回目) |
基本的には1回目のフィールド探索と同じ流れ(装備やステータスは引き継ぎ)だが,マップ構造や敵が変化する。 |
| ↓ | |
| 中ボス討伐 (2回目) |
1回目とは異なる中ボスが出現する。撃破時にはフィールド探索に戻らず,夜の王討伐に向けた決戦エリアに移動する。 |
| ↓ | |
| 夜の王討伐 | 最初に選択した「夜の王」が出現し,戦闘を行う。戦闘前には祝福に触れる機会が得られるため,体力と聖杯瓶の使用回数は回復する。 |
| ↓ | |
| 討伐達成 | |
ELDEN RING本編とどう違うのか
結論からいうと,基本的な操作システム以外はほぼ別物といえるほど異なる。ここからは,その内容を「仕様」「操作」に分けて説明していく。
●ELDEN RINGとの違い:仕様編
かなり項目が多く,個別に文章で説明しても分かりにくいので,いっそのこと現地でまとめたメモに補足情報を加えて掲載しよう。気になる項目があったら読んでみてほしい。重要度の高そうな項目には【重要】の表記をしているので,そこだけ見るのもアリだ。
| 移動力 | 通常の歩行,ダッシュに加えてスタミナを半分使用して「疾走」が可能。疾走中はトレント騎乗中に近い速度となる。壁に向けてジャンプをすると,1度だけ壁を蹴ってさらに上へと登れる。これを利用し,崖を登攀することも可能。 |
| 祝福 | HP回復,FP回復,聖杯瓶補充,レベルアップができる。触れた時点で回復し,聖杯瓶が補充され,ボタン連打でレベルが上がり,復活ゲージの長さがリセットされる。座る動作はなくなった。ダメージゾーンに飲まれた場合は利用できない。 |
| ルーン | 【重要】誰が,どこで敵を撃破したかを問わず,全員が獲得できる。ルーンを保持した状態で死亡した場合はそれを落とすが,付近に敵がいる場合は奪われることがある。対象を撃破すると,それを取り返せる。 |
| レベル | ルーンを消費して上昇させられる。能力値の割り振りは行えず,成長内容はキャラクターごとに固定になった。 |
| 聖杯瓶 | 初期上限数は3本。フィールドに配置される教会で光に触れると,上限数を増加させられる。教会の位置はマップで確認できる。独占は発生しない(誰かが拾ってもほかのプレイヤーのぶんが残る)。「青雫の聖杯瓶」の存在は確認できなった。 |
| 死亡処理 | 【重要】体力が0になるとダウンする。ダウン中,味方から攻撃を受けることで復活ゲージが溜まり,最大に達すると体力半分程度で復活できる。ダウンした味方はロックオン可。放置された場合,フィールドとボス戦で処理が異なる。 フィールド:一定時間で死亡。ルーンを落とし,最大レベルが1低下して復活する。低下したレベル差分を取り返すためのルーンも,落としたルーンに含まれる。 ボス戦:復活せず,時間経過で復活ゲージがカラになる。全員がダウンするとゲームオーバー。 復活ゲージは死亡するたびに長くなり,復活までに必要な攻撃数が増える。祝福に触れることで長さがリセットされる。 |
| インベントリ | 【重要】武器は計6本持てる(右手と左手それぞれに装備状態の武器1本,未装備の武器2本)。各種アイテムは4つまで所持可能。インベントリを超過して持つことはできないが,聖杯瓶はアイテムとは別枠として常に所持できる。 |
| 装備品 | 【重要】装備重量の概念が撤廃された。「装備可能レベル」が設定され,対応するレベルに到達しなければ装備できない。レアリティの概念があり,高レアリティなものほど装備可能レベルが高い。装備の強化も可能だが,レアリティに対応した鍛石が必要になる。ほぼすべての装備品には,未装備状態でもキャラクターにバフを与えるパッシブ能力がある。 |
| 宝箱 | 複数のアイテムが入っている場合がある。ドロップアイテムに近い扱いであり,誰かが取得したらほかのプレイヤーは取得できない。開く動作はなくなった。先行プレイでは罠宝箱,ミミックを確認できず。 |
| 落下ダメージ | 存在しない。いかなる高所から落下してもダメージを負わない。奈落に落下すると死亡する。 |
| 魔法/祈祷 | FPを消費して発動する。装備に紐付いた存在となり,単体での装備は不可能となった。装備から分離する手段は確認できず。魔法は主に杖の能力,祈祷は主に聖印に紐付いている。 |
| 矢/ボルト | 弓やクロスボウは対応する矢弾を無限に発射可能。 |
| 地図 | 最初からマップの全体像が明らかになっている。各プレイヤーはピンを打って意思疎通ができる。ただし,最初からすべての情報が書き記されているわけではない。地図を拾うと近隣に存在する重要な要素(スカラベの位置など)が追記される。 |
| 霊脈ジャンプ | トレントは存在しないので,体ひとつで跳躍ができる。霊脈の上に立って通常通りジャンプをするだけでOK。 |
| 接続 | クロスプレイは不可,同一プラットフォーム内の縦マルチ(PS4とPS5など)のみ対応予定。切断プレイヤーが発生した場合もゲームが継続され,後からの再接続が可能。 |
| バランス調整 | 挑戦人数が3人に満たなかった場合,敵体力などのバランス調整が行われる。敵のモーションや能力は3人プレイを前提に構築されているが,それらは変化しない。 |
●ELDEN RINGとの違い:操作編
ベースの操作システムに変化はないが,細かな仕様の変更に伴い変わっている部分もある。重要なのは移動系とアイテム系の挙動で,上記で紹介した「疾走」の追加,および「聖杯瓶」の非アイテム化による部分が大きい。
 |
まず,疾走は左スティック押し込みで発動する。本作ではスニークを必要とする場面がほとんど存在しないので,その枠に移動用のアクションが入った格好だ。ダッシュ自体の挙動にはほぼ変化がないので,問題になることはないだろう。
間違えやすいのはアイテムで,本作では聖杯瓶に専用のボタンが割り振られていた(試遊では[□]ボタン)。そのかわり,アイテムの使用は方向キーの[↑]が割り当てられており,戦闘中にアイテムを使う際にはちょっと手の動きに工夫がいる。
右手と左手の武器切り替えと同じ感覚で,人差し指を[L1]ボタンから離して方向キーを押すようなイメージだ。[L2]ボタンには戦技が割り振られているので,コントローラを間違えて押してしまわないように注意したい。
また,キャラクター固有能力である「スキル」「アーツ」については,スキルが[△]+[L2],アーツが[△]+[R2]に割り当てられている。[△]ボタンはアクション(調べる,開けるなどの動作)ボタンで戦闘中に押しても何も起こらないので,先に[△]を押してから[L2]か[R2]を押すような感覚で操作すればOKだ。
 |
NIGHTREIGN独自の要素について
本作の独自要素は多々あるが,特に重要なのが「キャラクター固有能力」と「遺物」の2点だ。ここでは,それぞれについて分かったことを紹介していこう。
●キャラクター「夜渡り」
本作のプレイアブルキャラクターは「夜渡り」と呼ばれ,それぞれが特殊なアビリティと,固有能力「スキル」と「アーツ」を持っている。いずれもクールタイムが設けられているが,スキルは汎用性が高い技,アーツは強力な必殺技という形で分けられている。
 |
リリース時点では8人のキャラクターが登場する予定で,今回のプレイでは,以下に掲載した4人のキャラクターを使用できた。現地で行われた紹介によると,登場キャラクターの中でも比較的扱いやすいメンバーとのこと。
| 追跡者 | |
|---|---|
| 概要 | あらゆる装備を使いこなす,バランスに優れた戦士系キャラクター。 |
| アビリティ | 第六感 本来死亡する攻撃を受けたとき,一度だけ自動でそれを回避する。 |
| スキル | クローショット グラップリングフックのような“クロー”を飛ばす。小さな敵は引き寄せ,大きな敵や地形に対しては自身が移動する。ガードを剥がす効果を持つ。 |
| アーツ | 襲撃の楔 パイルバンカーのような強力な一撃を打ち込む。地上,空中で使用可能。ボタン長押しで威力が上昇する。 |
| 守護者 | |
|---|---|
| 概要 | HP,スタミナが高く,初期装備に大盾を持つ。防御力に優れた騎士系キャラクター。 |
| アビリティ | ハイガード 強力なガード態勢をとる。 |
| スキル | つむじ風 風の渦を出現させる。範囲内の敵は渦の中央に引き寄せられ,軽量の敵は吹き飛ばされる。ボタン長押しで効果範囲が拡大する。 |
| アーツ | 救世の翼 跳躍後に落下攻撃を放つ。地上,空中で使用可能。着地時,ボタン長押しで味方を守るフィールドを出現させる。 |
| レディ | |
|---|---|
| 概要 | 技量や知力が高く,致命の一撃を狙いやすいスピード系キャラクター。 |
| アビリティ | 華麗な身ごなし 攻撃,回避アクションの消費スタミナを減らす。回避アクションを2連続で行える。 |
| スキル | リステージ 周囲の敵に対し,それぞれが直前に受けたダメージを再度与える。この効果は味方の攻撃にも適用され,攻撃や回避中にもノーモーションで実行できる。 |
| アーツ | フィナーレ 一定時間,自身と周囲の味方を不可視状態にする。 |
| 隠者 | |
|---|---|
| 概要 | 高い知力とFPで,魔法を効果的に活用できる魔法使い系キャラクター。 |
| アビリティ | 元素制御 魔,炎,雷,聖属性の攻撃を受けた敵に“属性痕”を発生させる。スキルで属性痕を収集した際,FPを回復する。属性痕は味方の攻撃によっても発生する。 |
| スキル | 混成魔法 通常時:対象が持つ属性痕を収集する。 属性痕を3つ所持:組み合わせに応じた魔法を発動。 発動する魔法は異なる属性の組み合わせほど強力な傾向にある。 |
| アーツ | 血魂の唄 自分中心の範囲内にいる敵に“血の烙印”を付与する。血の烙印を受けた敵は被ダメージが増加し,プレイヤーが攻撃した際にHPとFPが回復する。 |
●カスタム要素「遺物」
夜の王討伐に成功したか否かにかかわらず,討伐から帰還すると報酬としてランダムな「遺物」を獲得できる。遺物はキャラクターにパッシブ能力を与える特殊な装備品で,出撃時点でキャラクターの性能を変化させられる唯一の手段となる。
 |
遺物には「色」「大きさ」の概念がある。色は装備できるスロットの種類,大きさはレアリティを示しているようだ。一度に複数の遺物を装備することも可能だが,スロットごとに装備可能な色が設定されているので,誰でもなんでも装備できるというわけではない。
大きな遺物であるほど,同時に複数の効果を持っている。討伐がより深い段階に進むほど,得られる遺物のサイズは大きいものが増える傾向にある。夜の王討伐に成功した際には,3つの効果を持った遺物が複数ドロップした。
遺物から得られるパッシブ能力には「攻撃力強化」といったシンプルなものだけでなく,エスト瓶の効果を味方にも与えられるようになったり,特定の条件で自動でスキルが発動したりと,特徴的な効果も確認できた。さらに,一部キャラクター限定で効果を発揮する遺物も存在するようだ。
今回は確認できなかったが,遺物装備スロットの色を変更する手段も用意されているとのこと。こちらについては,今後の情報に期待しよう。
 |
約40分に濃縮された“成長と達成”
スピーディにRPG体験を味わえる
ざっと遊んでみて,感覚は非常に良好だった。なにより,プレイヤーキャラクターの挙動が機敏で,ストレスを感じる場面が非常に少ないのが良い。ワンセッションは夜の王討伐まで含めて40分程度かかるが,その間にヒマな時間は一切ないので,遊んでいたらあっというまに時間が過ぎていってしまった。
 |
敵から得られるルーン,遺物のボーナスなどはかなり気前がよく,武器更新やレベルアップによる能力上昇幅も大きいので,遊んでいてとにかく気持ちいい。所持数が限られている関係で,消費アイテム全般の効果が強くなっているのも含め,全体的に派手なゲームになった印象だ。
もちろん,ボス戦ではしっかりと緊張感があり,短いゲームループはセッション全体に良いメリハリを与えている。本作は“成長と達成”というRPGの流れを,40分間にギュッと詰め込んだ作品といえるだろう。
 |
 |
個人的に嬉しかったのは,許容されるプレイスタイルの幅の広さだ。ルーンが全員に行き渡る関係上,敵を倒しさえすれば必ず味方に利益を与えられるので,そこに至るまでのやり方は各プレイヤーに委ねられている。
味方に追従してフィールドにいる強敵と戦ってもいいし,1人で宝箱を開けまくって装備を集めて味方に提供してあげてもいい。キャラクター能力が個性的なこともあり,それを生かせるように動くことが良い結果につながりやすい仕組みになっているのだ。
今回のプレイアブルキャラクターは4人だったが,それでも「このキャラはこういう戦い方がいいんじゃないか」「この仲間のスキルと連携すると強そうだ」といった試行錯誤をジックリと楽しむことができた。これが8人となれば,相当奥深い遊びが楽しめるだろう。
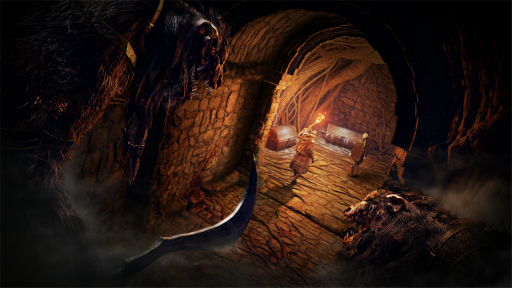 |
少し気になったのはマッチングの部分だ。本作は難度が固定,かつプレイヤーレベルの概念が存在しない関係で,いわゆる“野良”で遊ぶなら完全なランダムマッチングとなるわけだ。
ゲーム性に関わる部分ではないが,問題が発生しやすい要素ではあるので,何かしらの対策が用意されるかもしれない。
現地で確認したところ,正式リリース後にはプレイアブルキャラクターの追加DLCなども計画しているという(ただし,現時点では本編制作に注力しており,DLCの開発には着手していないとのこと)。まずは製品がリリースされてからの話になるが,そちらにも期待したいところだ。
「ELDEN RING NIGHTREIGN」公式サイト
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- 関連タイトル:
 ELDEN RING NIGHTREIGN
ELDEN RING NIGHTREIGN
- この記事のURL:
キーワード
- PS5:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PS5
- RPG
- MO
- バンダイナムコエンターテインメント
- ファンタジー
- フロム・ソフトウェア
- プレイ人数:1〜3人
- プレイ人数:1人
- 協力プレイ
- Xbox Series X|S:ELDEN RING NIGHTREIGN
- Xbox Series X|S
- PS4:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PS4
- Xbox One:ELDEN RING NIGHTREIGN
- Xbox One
- PC:ELDEN RING NIGHTREIGN
- PC
- プレイレポート
- ライター:蒼之スギウラ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C)2024 FromSoftware, Inc.
- 【PS5】ELDEN RING NIGHTREIGN 【数量限定特典】ジェスチャー「雨よ!」同梱

- ビデオゲーム
- 発売日:2025/05/30
- 価格:¥5,660円(Amazon) / 4690円(Yahoo)