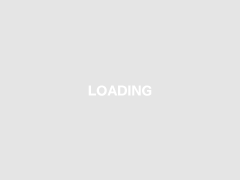イベント
鈴木 裕氏をはじめ,寺田克也氏や佐藤 大氏ら当時の関係者達が「バーチャファイター」20年前と未来を語った 「黒川塾(十伍)」聴講レポート
 |
15回目の開催となる今回のテーマは,「バーチャファイター/20年後の未来」。ゲストには,「バーチャファイター」のイラストを描き起こした寺田克也氏,メディアを通じて「バーチャファイター」の魅力を伝えた佐藤 大氏,ゲーム誌編集者のみならず,プレイヤー「新宿ジャッキー」としても活動していた羽田隆之氏,そして「バーチャファイター」の生みの親である鈴木 裕氏を迎え,リリース当時の「バーチャファイター」にまつわるトークを繰り広げた。
 |
トークの最初のテーマは,1993年12月にリリースされた「バーチャファイター」の企画開発を,鈴木氏が手がけることになった経緯についてである。当時,世間は対戦格闘ゲームブームで,セガの社長だった中山隼雄氏は,ことあるごとに「ストリートファイターII」の話ばかりしており,鈴木氏は,暗に「セガは格闘ゲームを作らないのか」と言われていると感じていたという。
一方,当時の鈴木氏は,直前に取り組んでいた「バーチャレーシング」の技術を応用し,3Dグラフィックスで人間を動かすゲームを実現できないかと考えていた。当初はサッカーやラグビーのような,多人数が参加するスポーツを題材にしたいと考えていたが,当時の技術ではキャラクターを2体程度に抑えないと処理が追いつかないという現実に突き当たる。そこで,ボクシングや格闘技なら2体のキャラで表現が可能で,かつ中山氏の要望に沿ったゲームができるのではないかと「バーチャファイター」を企画したのだという。
 |
しかし「バーチャファイター」の企画は,セガ社内でかなり反対されたと,鈴木氏は語る。というのは,当時の格闘ゲームブームのなかにあって,「ストリートファイターII」を超えたものは出てないという結果が,マーケットリサーチによって判明していたからである。要するに「今さら作る価値があるのか」という空気だったのだろう。
ただ結局は,3Dグラフィックスという差別化要素があるし,開発費くらいは回収できるだろうということで,「バーチャファイター」の開発はスタートする。
鈴木氏によれば,当時のスタッフは全部で15人くらい,そのうちデザイナーは一人もいないという小規模/低予算プロジェクトだったそうだ。
それでも「バーチャファイター」は,開発期間8か月程度というスピードでリリースに漕ぎ着けるのだが,その過程は順風満帆だったわけではない。鈴木氏は,プロジェクトが暗礁に乗り上げてしまうような大きな課題がいくつかあったとし,その中から,演算処理の速度を上げるために自ら機械語でプログラムを書いたというエピソードを披露した。
また3Dグラフィックスで,格闘技のリアルな動きを表現をすることも重要な課題だった。当時はモーションデザインという概念がなかったし,またスタッフ達も格闘技に関しては詳しくない。そこでスタッフ一同,パンチとキックを練習し,一とおり型ができるようになってから,初めてモーション付けの作業に取りかかったという。
 |
さらに鈴木氏は,格闘家の動きを再現するにあたっても苦労したことを語る。というのは,実際の拳法の動きには,100分の1秒単位で動いているものもあり,ゲームの30フレーム/60フレームという描画では表現しきれないのだ。そこで,あえて技の動きの速度を落とすようなこともしているのだという。
ちなみに「バーチャファイター2」以降はモーションキャプチャーを採用しているが,鈴木氏は,「手足の長いモデルの方がゲーム中での見栄えがよくなる」とも語っていた。
また,なぜ「バーチャファイター」がプレイヤーに広く受け入れられたかというテーマにも話が及んだ。それについて佐藤氏は,「ガチャガチャとデタラメにプレイしてもなんとかなるけれど,スポーツのように,やればやるほど上達する感覚があった」と語る。
その点に関して鈴木氏は,当時の格闘ゲームを自身でプレイしてみて,コマンド入力がうまくできなかったことや,3回に1回くらいはまぐれで勝ててもいいんじゃないかと考えていたことを明かす。
 |
そのため「バーチャファイター」の操作体系を決めるにあたっては,ハードルを下げるために,ゲームに詳しくない人達にレバーとボタンを操作させ,最も多かった組み合わせを基本技に振り分けたり,同じボタンを押しても相手との距離に応じて自動的に攻撃手法を切り替えたり――というようなことをやっていたそうだ。
また「バーチャファイター」では,同じく操作のハードルを下げるために,当時の格闘ゲームでは主流だった6ボタンではなく,敢えて3ボタンを採用しているわけだが,逆により多くのボタンを使う案もあったのだという。
鈴木氏は,スマートフォンなどのタッチパネルを使った操作のように,攻撃したい部分のボタンを押したり,あるいは押したボタンの数で攻撃の強弱を決めたりできるようなシステムを考えていたが,コスト面などの理由から見送られたそうだ。今のバーチャファイターの形からすると,一体どんなレイ感覚になるのか想像しづらいが,なかなかに興味深い話ではある。
さて。とにかくそんな試行錯誤の末に完成した「バーチャファイター」の登場を,メディアがどう受け止めたのか。当時ゲームライターだった佐藤氏は,「誌面に掲載される静止画では,このゲームの最大の魅力であるリアルな動きは伝えられない」と,最初は思ったという。
当時のゲームは,2Dグラフィックス表現が飛躍的に向上していた時代。そこに,段ボールをつなげたようなカクカクのポリゴンキャラを掲載したのでは,見劣りがするというわけである。
しかし,「バーチャファイター」を実際に触って衝撃を受けたメディア関係者やプレイヤー達は,逆に「何とかしてこの魅力を伝えなければならない!」という熱意を抱くきっかけにもなった,そしてその熱意が大きなムーブメントにつながったとのではないかと佐藤氏は分析する。
 |
一方で羽田氏は,「似たようなゲームばかりで閉塞感があったタイミングだったので,衝撃を受けた」と当時を振り返り,寺田氏も「段ボールのようなキャラが,リアルに動いている」と驚いた思い出を語る。ちなみに寺田氏は,「バーチャファイター2」にてキャラクターデザインの話を持ちかけられたときに,「『バーチャファイター1』は,こののっぺりした顔がいいんだから,このまま行きましょうよ」と発言したという。
そうした「バーチャファイター」のメディア露出を裏方として支えていたのが,当時セガの広報を担当していた黒川氏である。黒川氏は,ゲーム開発者達がインタビューを受ける場を設けたり,開発中の素材データの掲載を許可したりと,それまでのゲーム業界ではあまり行われていなかった事例を積極的に推進していった。会場では,顔出しNGの開発者のために,黒川氏が「バーチャファイター」のキャラのお面を手作りしたというエピソードも明かされた。なお,当時は新人だった寺田氏を「バーチャファイター2」のキャラクターデザインに推薦したのも,黒川氏だったのだそうだ。
 |
イベントの締めくくりで,未来の「バーチャファイター」に関して問われた鈴木氏は,「(レバーやボタンによる)入力がない方がいいのではないか」と語る。鈴木氏自身はあまりゲームを遊ばないので,どうしても操作面がおぼつかず,対戦では負けてしまうからだということなのだが,その解決方法のアイデアは独創的だ。
曰く,入力操作そのものをなくし,プレイヤーの頭で考えたそのままをセンサーで読み取り,判断で勝負できるようになれば,より面白くなるとのこと。ひいては「入力が変われば,ゲームも変わる」との持論を述べた。
さらに鈴木氏は,ホログラムを使ったゲームの実現などにも言及し,自身がセガに入社した頃と比較すると,現在のゲームには音と映像,インタラクティビティ,ネットワーク要素など,「今のゲームには,エンターテイメントのほぼすべての要素が含まれている」と語った。
最後に鈴木氏は,ゲームで今まで以上に大きな体験を提供するには,既成概念に縛られないことが重要であるとし,「夜空にレーザーで絵を描いて,あっちの宇宙とこっちの宇宙で対戦できたら楽しいよね」と例を挙げながら,イベントを締めくくった。
「バーチャファイター」が世に出てから20年。その過程で飛躍的な発展と進歩を遂げてきたゲーム産業だが,「バーチャファイター」に初めて触れたときのような驚きと感動を,また味わいたい――そんな気持ちにさせられたイベントであった。
 |
- 関連タイトル:
 Virtua Fighter 5 Final Showdown
Virtua Fighter 5 Final Showdown
- 関連タイトル:
 Virtua Fighter 5 Final Showdown
Virtua Fighter 5 Final Showdown
- 関連タイトル:
 Virtua Fighter 5(バーチャファイター5)
Virtua Fighter 5(バーチャファイター5)
- 関連タイトル:
 Virtua Fighter2
Virtua Fighter2
- 関連タイトル:
 Virtua Fighter2
Virtua Fighter2
- 関連タイトル:
 バーチャファイター5 Live Arena
バーチャファイター5 Live Arena
- 関連タイトル:
 バーチャファイター5 ファイナルショーダウン
バーチャファイター5 ファイナルショーダウン
- この記事のURL:
キーワード
- PS3:Virtua Fighter 5 Final Showdown
- アクション
- CERO B:12歳以上対象
- セガ
- プレイ人数:1〜2人
- 格闘
- 対戦プレイ
- Xbox360:Virtua Fighter 5 Final Showdown
- PS3:Virtua Fighter 5(バーチャファイター5)
- PS3
- PS3:Virtua Fighter2
- Xbox360:Virtua Fighter2
- Xbox360:バーチャファイター5 Live Arena
- Xbox360
- :バーチャファイター5 ファイナルショーダウン
- イベント
- 業界動向
- ライター:大陸新秩序
(C)SEGA
(C)SEGA
(C)SEGA
(C)SEGA
(C)SEGA
(c)SEGA
(C) SEGA