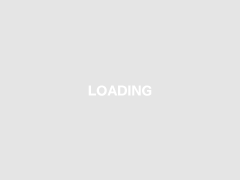「逆転裁判」シリーズの生みの親,巧舟氏による完全新作タイトル,ニンテンドーDS用ソフト「
ゴースト トリック」。今回カプコンブースにて初のプレイアブル出展がされており,これまで発表されてきた独自のゲームシステムに直接触れることができた。体験版の舞台そのものを模した特設ブースから,
試遊レポートをお届けしたい。
死者の力による,タッチペンとミステリーの融合
今回の体験版はゲームの導入部,主人公の死体を挟んで謎の男と女性が対峙しているシーンから始まる。男に銃を突きつけられ絶体絶命の窮地に立った女性の姿を,為す術もなく見守る主人公(死体)。だがそこで,謎の声によって“トリツク”“アヤツル”という二つの死者の力の使い方を教えられる。主人公は自分の身体を動かせない代わりに,周りのモノに取り付き“アヤツル”ことで生者の世界に干渉し,人の「死の運命」を変えるのだ。
操作はすべてニンテンドーDSのタッチペンで行う。下画面で主人公のタマシイを対象のモノにタッチ&スライドすると“トリツク”ことができる。とりついているモノの詳細は上画面に表示され,そのモノを“アヤツル”と何が起こるかが分かる。例えばギターに“トリツク”と「かきならす」ことができるため,ギターの音で男の注意を逸らして,女性が逃走するチャンスを与えられるのだ。
限られた時間の中で,正解のモノに辿り着け!
こうして説明すると,死者の力はあたかも万能のように思える。だが,遠くのモノや人間には“トリツク”ことができないため,目的のモノが近くにない場合は,周りにあるモノを中継して移動しなければならない。その際には,単にモノとモノを飛び石のように細かく渡って移動するだけでなく,ときにはモノを工夫して“アヤツル”ことも必要だ。例えば自転車を「こぐ」ことでタマシイを大幅に移動させれば,それまでとりつけなかったモノの近くにも行ける。
こういったモノとモノの組み合わせを考えることが,本作の謎解きの中心だ。「逆転裁判」シリーズは言葉のロジックで謎を解くゲームだったが,それに対して本作は,ドミノ倒しやルーブ・ゴールドバーグ・マシン(NHK教育「ピタゴラスイッチ」のピタゴラ装置のようなからくり装置)をパズル的感覚で作るような,非常に新鮮なゲームである。
また,一刻を争う場面には制限時間が設けられ,早く行動を起こさないと味方の「死の運命」を変えられずに終わってしまうこともある。限られた時間の中で冷静かつ素早く思考して正解に辿り着かねばならないが,画面に表示される吹き出しをタッチすれば“ヒトリゴト”というヒント機能を参照できるため,謎解きが苦手な人でも安心だ。
「タクシュー節」は健在,グラフィックスとの相性もバッチリ
体験版のクライマックスにちなんだデザインのストラップ。ネタバレは避けたいという人のため,サムネイルにモザイクをかけている(サムネイルをクリックすると,モザイクなしの画像が見られます)
![画像集#011のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/011.jpg) |
巧舟氏がディレクター・脚本を務めた「逆転裁判」シリーズの大きな魅力の一つに,個性的なキャラクター達の織り成すユーモラスな掛け合いがある。本作においてもその「タクシュー節」は健在で,死者が主人公という設定のシビアさを,掛け合いの妙で和らげている。また,本作のグラフィックスは独特のスタイリッシュな雰囲気を持っているが,そこに「タクシュー節」が合わさることで,見た目と中身の面白いギャップが生まれ,キャラクターの魅力を増しているのだ。
独特のゲームシステムにいち早く触れられるうえ,体験版のために特別に用意されたセリフもあるので,「逆転裁判」シリーズで「タクシュー節」の魅力に“とりつかれた”人はぜひ,会場で実際に試遊してみてほしい。会場で試遊した人には先着で特製ストラップがプレゼントされるが,この特製ストラップのデザインも,体験版を最後まで遊んだ人なら思わずニヤリとするもの。ファン必携ですぞ。
![画像集#002のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/002.jpg)
![画像集#001のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/001.jpg)
![画像集#003のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/003.jpg)
![画像集#004のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/004.jpg)
![画像集#005のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/005.jpg)
![画像集#006のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/006.jpg)
![画像集#007のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/007.jpg)
![画像集#008のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/008.jpg)
![画像集#009のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/009.jpg)
![画像集#010のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/010.jpg)
![画像集#011のサムネイル/[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/011.jpg)
 ゴースト トリック
ゴースト トリック









![[TGS 2009]弁護士の次は……死者が主人公!? 巧舟氏の贈る新作ミステリー「ゴースト トリック」の試遊レポート](/games/097/G009759/20090925002/TN/012.jpg)