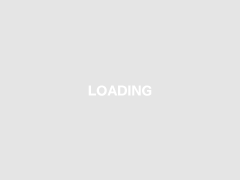ニュース
[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション
![画像集#001のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/001.jpg) |
アドベンチャーゲームの復権といっても,例えば近年のヨーロッパ市場におけるクラシカルアドベンチャーの豊饒さなどとは,別に関係ない。あくまで日本ゲーム市場におけるアドベンチャーゲームであるからして,かなり恋愛アドベンチャーに寄った話なので,そのつもりで読んでほしい。CEDEC 2007公式サイトにも明言されているが,登壇する顔ぶれから言ってもCEDEC 2006のセッション「恋愛SLG市場の成熟と家庭用ゲーム機への移植を中心に」のカヴァーバーションである。ともあれ,示唆的な話題が多々登場し,開発者をメインとするCEDECにはふさわしいセッションとなった。
テキストアドベンチャーからギャルゲに至る道
![画像集#002のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/002.jpg) |
テキストから始まったアドベンチャーゲームが,PCの性能向上に伴ってグラフィックス表現を取り込みながらも,依然として「マド ミル」といった単語入力方式で,キーワード探しに血道を上げなければならないまま……ところから,やがて,あらかじめ用意された選択肢を選ぶだけの「コマンド選択式」が考案されたことで,コンシューマゲームのパッド入力にも対応可能となっていく。
そうして,「ポートピア連続殺人事件」など,PCゲーム市場での傑作アドベンチャーゲームがファミコンに移植され,それを追いかける形でファミコン独自の作品が登場,ディスクシステムの時代に入ってからホラー/ミステリージャンルの良作が続々とリリースされる。また「かまいたちの夜」「弟切草」といったサウンドノベルのヒットで成立した,周回プレイを前提としたスタイルが,恋愛アドベンチャーやアダルトソフトの展開にも影響を与えたと,氏は主張する。
![画像集#006のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/006.jpg) |
![画像集#007のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/007.jpg) |
![画像集#008のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/008.jpg) |
![画像集#009のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/009.jpg) |
![画像集#010のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/010.jpg) |
![画像集#011のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/011.jpg) |
![画像集#003のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/003.jpg) |
さて,話題は変わってPCゲームである。1980年代のPCゲーム界には,原作モノアドベンチャーゲームの独特の盛り上がりがあったとする。その立役者はエニックスの「ウィングマン」,マイクロキャビンの「めぞん一刻」などだ。この路線をさらに推し進めたコンシューマゲームでの作品例が,漫画家との全面的コラボレーションに踏み切ったゲームアーツの「ゆみみみっくす」(1993年)であるという。
こうした流れにやがて合流するのが,「プリンセスメーカー」や「ときめきメモリアル」を源流とする,1980年代後半,PCでのキャラクター/恋愛シミュレーションである。パラメータ育成をゲーム性の核としていた恋愛シムの流れが,キャラクター性とストーリー性の前面化によって,アドベンチャーゲームに寄っていく。これが,1990年代後半に本格的なギャルゲブームを到来させたという。
そうして,「とりあえずギャルゲーならいいんだろ?」という開発側のフリーハンドが,より深いストーリーやテイストを拓いていく。吉田氏はこの「とりあえず……ならいいんだろ?」状況を,秀作ゲームが誕生する一つの契機として強調した。
その後,1990年代後半から2000年代にかけて,コンシューマゲームでのアドベンチャーが,アニメ作品のマルチ展開として市場に氾濫するも,これはあまり意欲的な試みを含まないものが大半で,アドベンチャーゲームのいったんの沈滞を招く。対して,PCアダルト市場ではノベル系作品が全盛を迎え,これがしばしばコンシューマゲームにサビ抜き移植されるという流れが出来る。
![画像集#012のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/012.jpg) |
![画像集#013のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/013.jpg) |
![画像集#014のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/014.jpg) |
![画像集#015のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/015.jpg) |
![画像集#016のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/016.jpg) |
![画像集#017のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/017.jpg) |
一方,新興市場である携帯型ゲーム機では,パズルゲーム主体の市場から,「逆転裁判」のヒットなどを通して,次第にアドベンチャーゲームに注目が集まり始める。ニンテンドーDSの性能をもってすれば,1990年代までのアドベンチャーゲームの傑作も,おそらくはスムースに移植可能だ。そして隙間時間利用という意味あいがさらにはっきりしたケータイゲーム市場では,短時間のプレイの積み重ねが可能なアドベンチャーが,今後再度脚光を浴びるだろうというのが,吉田氏の分析である。
![画像集#018のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/018.jpg) |
![画像集#019のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/019.jpg) |
![画像集#020のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/020.jpg) |
![画像集#021のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/021.jpg) |
![画像集#022のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/022.jpg) |
![画像集#005のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/005.jpg) ベック 芝村裕吏氏 |
また,吉田氏が「とりあえず……ならいいんだろ?」状況を敷衍して「とりあえず萌えならいいんだろ? となった現状の帰結が非常に楽しみ」と述べたのに対し,サブカル評論で名高い哲学者/評論家の東 浩紀氏が「僕はそれが『らき☆すた』だと思う」と,たいへん的確な(……いや,何に対してかはさておき)補足を行っていたのが印象的だった。
果たして初期PCアダルトゲームに,コンシューマゲームのサウンドノベルがそれほど影響を与えたか,時間的には並行関係ではないか? という疑問や,例えばコンシューマゲーム機については,プラットフォーム末期にギャルゲ移植が多発することなど,同時に考察すべき論点はほかにもいろいろあるように思われるが,とりあえず現在までの国内アドベンチャーゲームの通史というべきものを実に手際よくまとめて,吉田氏のセクションは終わった。
オタク消費の受け皿として独自の発展を遂げる
![画像集#023のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/023.jpg) |
氏によれば,コンシューマゲーム機の世代が新しくなるにつれて開発費が高騰,世界市場に向けた大作に力が注がれる一方で,手堅く稼げるアドベンチャーゲームが見直されているという。
![画像集#024のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/024.jpg) |
![画像集#025のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/025.jpg) |
![画像集#026のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/026.jpg) |
ゲーム機の進化による表現の深化は,むしろ文化圏ごとの表現の違いをも生み出す。その日本における一つの形が,アドベンチャーゲームの隆盛だったという。声優さんによるキャラクターボイスや,アニメ作品のオリジナルシナリオといった,オタク層の要望を安価な形で満たす手段を実現し,セールス数も読みやすいタイトルが,世界市場への挑戦という大目標の反作用で進んだのだという。
そして今後の展望としては,参入メーカーの増加によって,よりクオリティの高い作品が生き残るであろうこと,また,ニンテンドーDSやWiiの登場で,違った切り口の作品が生まれて行くであろうことを指摘した。
二重の差別化努力が生んだ「デモンベイン」
![画像集#027のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/027.jpg) |
話題にするタイミングとしては,いささか遅めな気もするが,デモンベインという作品の成立について当事者が語るドキュメントとして,また,一つのブランドを確立し得たメーカーが採り得る戦略として,参考になる考え方だろう。
氏はデモンベインのコア部分を,クトゥルー+熱血スーパーロボットものと総括,その依って来たるところを語る。ニトロプラスが参入する頃のPC美少女ゲーム業界が,Leafのビジュアルノベルシリーズに端を発する流れによって,物語に特化した市場となっていたと,ひとまずまとめる。つまり,泣きゲーの全盛期こそが,ニトロプラスが最初に見た市場の姿であった。
そこに新規参入するニトロプラスにとって,差別化こそが最初の課題だった。「Air」と同じ2000年に登場したデビュー作は,ハードボイルドな内容を特徴とする「PHANTOM OF INFERNO」であり,既存の美少女ゲームにはあまり見られない内容で注目を浴びた。これが,当面のニトロプラスの作風を決定づける。
これに続く「吸血殲鬼ヴェドゴニア」は吸血鬼モチーフでヒーローものをやろうという内容,「鬼哭街」はサイバーパンクでカンフーアクションをさせながら復讐劇をやろうという内容で,いずれもダークな背景を特徴とする。そして,これら作品を世に送り出してきたのが,ニトロプラスのメインシナリオライター・虚淵玄(うろぶちげん)氏であった。
![画像集#032のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/032.jpg) |
![画像集#033のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/033.jpg) |
![画像集#034のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/034.jpg) |
![画像集#035のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/035.jpg) |
![画像集#036のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/036.jpg) |
![画像集#037のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/037.jpg) |
さて,ここからがようやくデモンベインの話である。デモンベインの課題は,バトル/ハードボイルド/銃器/メカニック/3D CGといった,ニトロプラスならではの要素を生かしつつ,既存のニトロプラスにはなかったものを作り上げるところにあった。「劣化虚淵玄はニトロプラスに必要ない」という鋼屋氏の認識は,実に端的なものである。
虚淵玄作品の特徴が,ハード/ストイック/洗練された何かであったとすれば,鋼屋ジンはその逆を行かねばならない。すなわち,ライト/派手/雑然とした何か,だ。これらはニトロプラスの得意な要素と併せて,荒唐無稽なスーパーロボットという方向性と合致する。そして,重厚なクトゥルー神話とアニメ的なノリ,キャラクターの悲劇的な過去と喜劇的なふるまいなど,相反するものを幾重にも重ねた作品,きれいに落ち着くことを拒んで最適解を裏切るものを目指す作品がデモンベインであり,矛盾が持つパワーこそが創作のテーマなのだという。
自ブランドのアイデンティティを重視した結果,萌え路線を途中で放棄した作品をもラインナップに持つニトロプラスの,二重の差別化努力の結実が,まことに騒がしいロボット活劇のデモンベインであったという経緯は,なかなかに興味深い。その騒がしさと,いささか衒学的な(?)設定の組み合わせが,アニメ版でも威力を発揮して,今日の人気があるのだろう。
![画像集#028のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/028.jpg) |
![画像集#029のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/029.jpg) |
![画像集#030のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/030.jpg) |
![画像集#031のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/031.jpg) |
コミュニティによるコンテンツ享受と「ひぐらし」
![画像集#038のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/038.jpg) |
ひぐらしが話題になるに当たって,内容の面白さはもちろん重要なファクターだったのだが,それはあくまで,触れてみなければ分からない事柄である。そこで,多くの人が手に取った(ダウンロードした)理由を突き詰めていくと,「正解率1%」という挑戦的なキャッチコピーのインパクトにあったのではないかというのが,浦野氏の見解だ。
![画像集#040のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/040.jpg) |
![画像集#041のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/041.jpg) |
![画像集#042のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/042.jpg) |
![画像集#043のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/043.jpg) |
![画像集#044のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/044.jpg) |
![画像集#045のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/045.jpg) |
氏によれば,このキャッチコピーは初期βテスター100名のうち,ただ一人が原作者の想定した正解に到達したという事実に基づいているとのこと。この挑発が効を奏してプレイヤーが集まり,そこから口コミで評判が広がって,コミュニティが形成されたという。
![画像集#046のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/046.jpg) |
![画像集#047のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/047.jpg) |
![画像集#048のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/048.jpg) |
![画像集#049のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/049.jpg) |
![画像集#050のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/050.jpg) |
![画像集#051のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/051.jpg) |
![画像集#052のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/052.jpg) |
![画像集#053のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/053.jpg) |
![画像集#054のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/054.jpg) |
![画像集#055のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/055.jpg) |
![画像集#056のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/056.jpg) |
![画像集#057のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/057.jpg) |
![画像集#058のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/058.jpg) |
![画像集#059のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/059.jpg) |
![画像集#060のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/060.jpg) |
![画像集#061のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/061.jpg) |
そうした移植と多メディア展開を可能にしたのは,原作者が“良い意味で”固執せず,それぞれのメディアにおけるプロ達に任せられたことだという。コミックやテレビアニメ,コンシューマゲームなど各メディアの担当者達は,原作者たる竜騎士07氏の穏やかで腰の低い人柄を核として緩やかなネットワークを形成し,「自分のところではこうやるから,続く作品ではこうしたほうが」といった連絡を,とくに気負いなく取り合え,互いに敬意を抱ける環境が出来ていたという。そしてそれらの相乗効果が,多くのファンを育てたとのことだ。
若干の韜晦をにじませつつ,そうしたポジティブなネットワークを支える関係性を,「人柄」や「愛」といった概念でかみ砕いて説明するあたりが,いかにも浦野氏らしい物腰であった。
![画像集#062のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/062.jpg) |
![画像集#063のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/063.jpg) |
![画像集#064のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/064.jpg) |
![画像集#065のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/065.jpg) |
![画像集#066のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/066.jpg) |
![画像集#067のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/067.jpg) |
![画像集#068のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/068.jpg) |
![画像集#069のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/069.jpg) |
![画像集#070のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/070.jpg) |
![画像集#039のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/039.jpg) |
東氏の見解によれば,ここ7〜8年のノベルゲームは,それ以前にゲームと呼ばれていたものと切り離された消費形態を展開しており,それは単なるマニア/コアユーザーとは違うという。その端的な表れが,1990年代半ばから,操作と視聴覚刺激(絵が動く/絵がキレイ)への関心を失って,物語を読むことに関心が移っているように見える点だとのこと。その極点に位置するのが,「ひぐらしのなく頃に」であったという。
そして,氏の近著である『ゲーム的リアリズムの誕生』の論点に沿ってコンテンツ指向型消費とコミュニケーション指向型消費の概念について述べ,後者を「一つのコンテンツが提案されて,その周囲にコミュニケーションの輪が広がると,その輪も含めた全体がコンテンツになる」という構図だとした。
どうやって原作者にお金が落ちるかという話とはまったく別に,社会現象として見た場合,「ひぐらしのなく頃に」の周辺には,それについて語った膨大な人達がいて,経済には織り込まれない形で情報のやりとりや噂話の授受が起きている。東氏によればその全体が「ひぐらし」なのであり,アーリーアダプター以外の人にとっては,その全体がコンテンツとなる。
そうした現象は,インターネットの普及以降広汎に起きており,アニメ「らき☆すた」,それに先行するアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」が好例だという。東氏の意見では「涼宮ハルヒ」のブレイクにはYouTubeの普及が密接に関係している。動画をblogに貼り付けることにより,みんなでコメントを書きあえるという形に乗ることで,「涼宮ハルヒ」がブレイクし,その後を襲ったのが「らき☆すた」というわけだ。また氏は「京都アニメーションの“うまさ”は,そうした流れ,コミュニケーションを作り出す部分にあり,コンテンツそのものを論じても始まらない。実はひぐらしもそのように機能した」とも付け加えた。
一方芝村氏は,浦野氏の講演後半で強調された人間関係要素の重要性を再度強調するとともに,多メディア展開の動向について補足,「2000年代に入ってから,ゲームをアニメにしたときの成功例は多い一方で,アニメをゲームにしたときの成功例は減っている」と,なかなか重要な問題提起をした。
セッション冒頭で吉田氏が触れた,1980年代PCにおける意欲的なアドベンチャーゲームの話と,1990年代にコンシューマゲームで量産されるアニメーションの多メディア展開としてのアドベンチャーゲームの話に,おそらくはつながる論点だろう。
内容で勝負? 切り口で勝負?
![画像集#071のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/071.jpg) |
最初に例に挙がったのは,原田氏が10年ほど前にディレクターとして携わった,男女両側の視点からプレイできる恋愛アドベンチャー「e'tude prologue 〜揺れ動く心のかたち〜」の開発である。ディレクターとしては,制作チームに何ができて,どこが問題かを把握するのが重要なのだが,ここで問題となったのは,スタッフが恋愛アドベンチャーゲームを知らないことだった。
そこでどうしたか。恋愛アドベンチャーは知らなくとも,テレビドラマであれば全員イメージできる。そこで,男女両側の視点というコンセプトはそのままに,ドラマ仕立ての作品を作ろうという方針を打ち出したという。
そこで課題となったのは,果たしてドラマ仕立てが,プレイヤーの求めるものであるかという点,そして,男女両方の視点を持つことで,ストーリーにおけるターゲット層をどちらかにはっきり絞れないという点だ。
その解決に向けて打ち出された具体策の話は,作品論になるのでさておき,講演はここでディレクター的視点に立ち戻る。新しく見えるシステムの多くは,たいがいすでに誰かが考えついているのであって,それが実現していないのは,そこで生起する問題の克服に成功しなかったからだと,原田氏は考えたという。
であるとすれば,「問題があるからやめましょう」では,新しいものは永久に作れないわけで,具体的な問題の解決に取り組むことが,制作上肝要なところだという。
![画像集#072のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/072.jpg) |
![画像集#073のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/073.jpg) |
![画像集#074のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/074.jpg) |
![画像集#075のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/075.jpg) |
作品を作っていくうえで,氏は三つのプレイヤー層を想定して,それぞれの反応を意識するという。その一つめは「アドベンチャーゲームのファン」で,この層はオーソドックスな意味での作品のクォリティに厳しい。二つめが「アクションなどほかのゲームのファン」で,読むだけでは物足りないと感じる可能性がある。三つめが「ライトゲーマー」で,レンタルビデオで映像作品を楽しむ感覚に近いため,より価格と内容のバランスに関してシビアだ。
そうやって考えていったときに,氏が考える正解は大別して二つ。一つはオーソドックスなスタイルで,ストーリーや演出面で勝負するというものだ。アドベンチャーゲームファンに向けて,こだわりを発揮するやり方である。二つめは,アドベンチャーゲームのあり方そのものを考え直すというもの。この方法を採ったときに考えるべき問題が,先ほどの問題解決というわけだ。
氏は最後に最近手掛けた/手掛けている作品3本を例示し,それぞれどこで勝負すると考えたかを,照らし合わせて見せた。
ジャンルの本格成立までのストップギャップ=アドベンチャー
![画像集#076のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/076.jpg) |
1.ストーリー性を有し
2.プレイヤーが意志を入力する場面があり
3.コンピュータからの応答をもって娯楽とする
だがこれらは,よく考えてみればほとんどのゲームに当てはまる項目である。そしてそのことこそが,論旨のうえで重要なポイントになる。このような現象は,「ゲームの分類に困ったら,とりあえずシミュレーションかアドベンチャーにしておけ」という慣行の産物であると,芝村氏は指摘した。
そこで,吉田氏の説明とも関連づけつつ,成立順にアドベンチャーゲームを分類すると,それはまず「テキスト入力/テキスト出力」から始まったことになる。そして,この段階でマルチエンディングが成立していない理由として,作業量の問題を挙げる。
テキスト入力に答えを返すためには,実のところ背後に膨大な単語想定と応答のテキストが必要である。黎明期のテキストアドベンチャーでは場面ごとの管理こそできていたが,応答に更なる適切な応答が連なっていくというチェーン管理はできなかった。
テキスト入出力の作品に,やがて加わったのがグラフィックス表現。日本で紹介された作品はこの段階以降であるが,そこでもまだマルチエンディングは達成されていない。
そうした第二世代(グラフィックス表現あり)のアドベンチャーが栄えたあとに,各メーカーの差別化努力によって進化の方向性が三つに分岐する。その一つめが,コマンド選択方式からマルチエンディング化に向かう流れである。そして二つめがテキスト出力を捨てて,グラフィックス中心で行こうという方法だ。「MYST」が代表作だが,やはり制作に並々ならぬ手間がかかるということか,その後の進展があまり見られない。そして三つめは,ほかのゲームジャンルとの融合である。戦闘シーンはアクションであるとか,そういった形だ。
![画像集#077のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/077.jpg) |
![画像集#078のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/078.jpg) |
![画像集#079のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/079.jpg) |
先ほどの定義の話からも分かるように,アドベンチャーゲームは古いジャンルであり,シンプルな形でも成り立つのが特徴だ。そうしたわけで低スペック,低予算,小規模開発への適応を進めてきた。セリフに加えて地の文を使えるぶんだけ,スラップスティックから哲学論争まで表現の汎用性に優れる一方で,それがプアなハードウェアスペックと開発資産で実現するため,小規模なプラットフォームほど相対的に強くなるのが,アドベンチャーゲームの特質だ。氏は分かりやすい例として「鋼屋ジンさんの世界観をほかのゲームジャンルでフルに実現しようと思ったとたんに,たいていは予算が足りなくなります」と述べた。
そうしたアドベンチャーゲームの生存戦略(?)は,「その分野に適したゲームジャンルが編み出される前のストップギャップ」を埋めるものとして,過渡的に存在するという。そして,これまでの生存と適応の方向性から見て,
A.開発の規模がさして大きくなく
B.発展途上で決定打に欠けるジャンル
に限って,アドベンチャーゲームが主力となり得るという。例えばアドベンチャーゲームの可能性や復権といった話題は,上記二つの条件が同人業界の立ち位置にぴったり合致しているがゆえに,アリだという話になっているのだと整理する。アドベンチャーゲームで儲かったお金は,往々にしてゲームシステムに回り始め,それによってゲーム性の付与が行われるようになる。その意味でアドベンチャーゲームの復権とは,市場が冒険的ステータスにあるとき,一瞬だけ存在する徒花のような存在だというのが,現状に対する芝村氏の見解であった。
それでキャラクターゲーム市場のあり方(つまり,ぎりぎりまで「見るもの」に近い市場)を説明できるか否かはさておいて,市場を巨視的に捉える意味では,たいへん示唆的な見解といえよう。
![画像集#080のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/080.jpg) |
![画像集#081のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/081.jpg) |
![画像集#082のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/082.jpg) |
![画像集#083のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/083.jpg) |
だが,芝村氏の考察はさらに続く。あくまで技術屋が考えた一例と断りつつも,氏はもし,真の意味でのアドベンチャーゲームの復権があり得るとしたら,それはどういった形になるだろうかという思考実験を繰り広げる。
氏はアドベンチャーゲームの進化史を逆にたどり,過去に解決済みとされている事柄に,現在ならではの別のアプローチをもって臨むことを考える。アドベンチャーゲームが現在のような形に進化していったのは,そもそもテキスト入力方式に限界があったからだ。つまり,現在の技術でこの限界を突破できれば,まったく新しい展開が見えてくるということである。
PCの普及が大きく進んだ現在では,キーボード入力に対するプレイヤー側の抵抗感も少ないし,そもそも携帯電話で文字が入力できるご時世である。自然言語に近いプレイギミックも,現在なら可能かもしれない。テンポの悪さという問題も,ここまでに積み上げられた演出上のノウハウや,状況に合わせたコマンド選択の併用などで解決可能ではないかというのが,氏の意見だ。
ゲストスピーカー堀 幸司氏……の予定稿
![画像集#084のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/084.jpg) |
「リフレインラブ制作をしていたあの頃」と題された予定稿では,ギャルゲの皮をかぶった正統アドベンチャーを目指したことが述べられ,第1作における横512ドットモードへの挑戦や,第2作におけるラジオドラマ的制作方針,「そこに世界がある/空気があるという感覚」を目指したことを述懐,最後に,いまやニンテンドーDSで同レベルの作品が開発可能であろう現状に触れ,アドベンチャーゲームの明るい展望を述べて終わった。
![画像集#085のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/085.jpg) |
![画像集#086のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/086.jpg) |
![画像集#087のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/087.jpg) |
![画像集#088のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/088.jpg) |
![画像集#089のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/089.jpg) |
![画像集#090のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/090.jpg) |
ライトユーザー・開発予算・燃え。多彩な質疑応答
![画像集#091のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/091.jpg) |
推理ものであれば,謎解きを進めるNPCを設定し,プレイヤー自身で謎を解くことができれば,相づちを打つだけになるような仕組みが考えられると。ただし,いずれにせよアドベンチャーにおける自動進行は,プレイ時間を縮めてしまうという問題もはらむので,その点は要注意であるとも言い添えた。
また,現在ニンテンドーDSでアドベンチャーが売れている理由と,ライトユーザーを意識したとき,今後アドベンチャーがどうあるべきかについては,キャビアの牧野氏が回答した。氏によると,ニンテンドーDSタイトルの卓越点はインタフェースで,凝っていて,反応を目で楽しめるように作られているという。そうしたこだわり,フックのあるタイトルが売れているのだそうだ。
続いて牧野氏が答えたのは,低予算といわれるアドベンチャーゲームの損益分岐点について。会社ごとに宣伝費と販売管理費の計算が異なるので一概に答えられないとしつつ,PS2向けのタイトルであれば,1億かけて7〜8万本という,一般的な目安を示した。
![画像集#092のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/092.jpg) |
氏はさらに論点を掘り下げ,Keyの泣きゲーによっていびつになったアドベンチャーゲームの世界を,Fateが戻したのではないかという,東氏との意見交換の結果を話す。そして「ハルヒが流行ったからといって,SF+学園ものならOKではないし,誰もピンと来ない。もはやジャンル云々が問題ではなく,今後,これがトレンドといった明確な形は生じにくいのではないか」という見通しを述べ,「燃え」が独立ジャンルたり得なかった理由については,「TYPE-MOONさんが強すぎて,誰がやってもその延長として受け取られるに留まった」という,氏なりの印象を披瀝した。
鋼屋氏の説明の前提部分を,さらに東氏が補足する。東氏はゲームの観点からアドベンチャーゲームを位置づけた芝村氏の説明内容を高く評価しつつ,一方で物語としてのアドベンチャーゲームが,ライトノベルなどに近いジャンルであることを確認,それゆえにジャンルの栄枯盛衰を決めているのは,システムではなくシナリオの中身であり,それはシステムの進化などとはまったく別に存在し,それをたどることでまた違った歴史が描けるはずと述べる。
アドベンチャーゲームを,もっぱら物語の観点で追う東氏によれば,その内容には社会状況も関連しているという。氏がいささか戯画化/単純化して述べたところでは,1990年代後半の不況で,若年層が未来に絶望していたタイミングで流行ったのが泣きゲーであって,景気が良くなってくると,ドカンと強い主人公が求められるといった具合なのだそうだ。
そうした意味で1990年代の後半が,ここ20〜30年の日本社会でも特殊な時期であり,自分のエネルギーをどこにも持って行けない20代の男子が,ネットワークという新しいインフラのアーリーアダプターとして現れた。そこで栄えたのが泣きゲーだが,いまやその歴史は終わって違うフェーズに入っている。泣きゲーは特殊な空間で作られたのであり,現在はもっと普通のものが主流を占めている。これは,ライトノベルの傾向とも一致しているという。
![画像集#093のサムネイル/[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/093.jpg) |
その豊富さを豊富さのままに取り上げたのが,このセッションの規模につながったといえようか。いささか詰め込みすぎの感があり,個々の論点について丁寧に扱われていたとは言い難いものの,逆に言えば誰の立場から見ても,何かしら新鮮な切り口に触れられるという意味で,実りの多い内容だったといえよう。
- 関連タイトル:
 機神飛翔デモンベイン
機神飛翔デモンベイン
- この記事のURL:
キーワード
- PC:機神飛翔デモンベイン
- PC
- SF
- シングルプレイ
- ニトロプラス
- ファンタジー
- ホビボックス
- ロボット
- 格闘
- 日本
- 恋愛
- ニュース
- イベント
- 業界動向
- 編集部:Guevarista
- CEDEC 2007
(C)Nitroplus



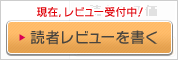






![[CEDEC 2007]デベロッパ,パブリッシャ,学識者の豪華メンバーが集った「アドベンチャーゲームの復権」セッション](/games/030/G003007/20071003004/TN/094.jpg)